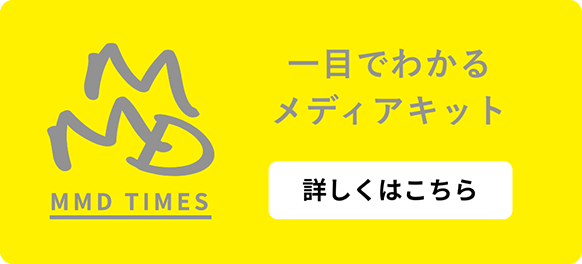Contents
人が馨 (かお) るモノづくりを

モノづくりの進化と文化の発展についてまわる課題とは何か。
戦後の技術革新と大量生産は我々の生活を便利で豊かにする一方、熟練工や職人の活躍の場、その機会をじわじわと奪ってきた。
特に伝統工芸の従事者数は年々減少・高齢化し、後継者不足が叫ばれる現代。これは志願者不足など単純な原因ではなく、売上の減少が大きく関係している。
工芸品をはじめ職人がつくるモノが売れないことには、人を雇うことは疎か、自身の生活もままならない。
つまり伝統工芸継承のためには、その工芸品の認知と売上が第一に優先されるべきである。

「丸亀うちわをご存知ですか?」そう切り出すのは株式会社キャライノベイトの代表取締役社長 清水 篤 (シミズ アツシ) 氏。
それまで順風満帆にフレグランス企業でキャリアアップしてきた経歴を捨て、小さな倉庫でひとり、香りの会社を設立。
「10年以上前、そのうちわをつくれる職人がご高齢で僅かしかいないことに衝撃を受け、モノづくりの考えを改めました」
今年で14年を迎えるという同社だが、日本の地域や伝統、そして文化に根ざしたメイドインジャパンへの想いは設立当初から変わらない。
「これまで培った香りの知識とモノづくりを通して日本を元気に」この想いがつくった日本の伝統工芸、文化、そして職人を救うカタチを取材した。
これからのモノづくりのあり方とはどうあるべきなのか。

株式会社キャライノベイト https://kyarainnovate.jp/ 地域・伝統・文化にフィーチャーし、メイドインジャパンの香りを活かしたモノづくりを行う企業。アロマオイルや石鹸、ミストなど、“香り”を軸にオリジナル商品やOEMの企画・製造を行う。「『楽しい会社』で、『新たな伝統を創る』」を理念に、日本の伝統と伝承を尊重したプロダクトが特徴。
香りで新たな伝統を創る

会社設立のきっかけを教えてください。
− 清水氏コメント:日本の素晴らしい伝統工芸への感動と同時に、職人の減少と高齢化を目の当たりにしたことで、日本のモノづくりへの危機も感じました。
「この現状をどれだけの人が知っているのか、自分にできることはないのか」と。
ちょうどその頃、以前に勤めていた会社から「役員にならないか?」と打診を受けていたんです。
でも、あの日以来「安ければ良いというモノづくりではなく、物を大事にするモノづくりをしたい」という想いが強くなっていき、今がタイミングかもしれない、と一念発起で退職し、会社を設立しました。

「株式会社キャライノベイト」とはどのような会社なのでしょう?
− 清水氏コメント:日本各地で採れる素材を原料にしたり、日本が誇れる職人の技を守り続けるべく現代のテイストを融合させたフレグランスアイテムを展開する会社です。
単に香り商品を扱うのではなく、「日本の伝統を残し、新たな伝統を創る」ことが目的なのが特徴です。
過疎化や高齢化、後継者不足によって危機に陥っている伝統や文化を“香り”というフィルターを通し、認知させることが狙いです。

− 清水氏コメント:また、企業メッセージとして「『人が馨 (かお) る』世の中へ。」を掲げています。
“馨る”という字には、人やその人の良い評判が伝わるという意味があるんです。
我々は“香り”を通じて、生産者や商品に関わるヒト、その評判が伝わるモノづくりを心掛けています。
その商品にどのような人が関わり、どういうストーリーでつくられるのか、背景にある“コト”をしっかり伝え、価値を理解してもらいモノが売れる。
さらに売れ続けることで、それが新しい伝統を生む、そういうプロダクトの開発をしています。
香りの“その先”に光を

具体的にどういった商品があるのでしょう?
− 清水氏コメント:ちょうどSDGs (エスディージーズ) が採択された2015年、「WANOWA (ワノワ) 」というブランドを立ち上げました。
ある製品の製造過程で廃棄されていたものを原料にして、香り商材をつくっています。
第1弾は石川県能美市の柚子の果皮を使用してハンドクリームやローションなどのスキンケアアイテムをつくりました。

− 清水氏コメント:石川県が柚子の産地でもあるのをご存知ですか?柚子と聞くと高知県や徳島県など、四国をイメージされますよね。
能美市には「柚子味噌」という郷土料理があるほど、地域の人々にとって柚子は身近な農作物でした。
ところが現在は、還暦を超える農家さん数名で管理をするほどに縮小し、生産量や認知度は他の地域と圧倒的な差があります。
このままでは能美市の文化と農産物が途絶えてしまう。この問題を香りで解決できないかと考えました。

− 清水氏コメント:実は、能美市の柚子は30年以上も無農薬・有機で栽培している、非常に質の良いものなんです。
我々はここに着目し“オーガニックの国造ゆず”からできたコスメを謳うことで、能美市の柚子の認知拡大を図りました。
地元の方々は、自分たちが当たり前のようにしてきた無農薬や有機栽培が大きな価値だと思っていないようですが、世界的にオーガニック需要は年々高まっていますよね。
このように、良いモノづくりの現場に“新たな視点”を与えることで、それが世の中に拡がる仕組みをつくっていきたい。
あくまでWANOWAはヒト・モノ・コトを“伝える”役割で、最終的にはそのモノ自体の売上に貢献したいと思っています。

− 清水氏コメント:また、継続的に生産を行ってもらえるよう支援も欠かせません。商品の売上の2%は生産者へ還元しています。
ブランド立ち上げから3年半経った2019年には、還元した売上で約30年ぶりに柚子の苗木40本を植樹しました。
地元でも柚子が採れることを知らない方々がいる中、地域の子ども達が参加して地元の農産物を学ぶ姿や農家の皆さんが涙ながらに喜ぶ姿を目の当たりにしました。
単純にモノをつくって売る、というビジネスにはないストーリーがここにはあります。
その瞬間に立ち会った時、我々の信じているモノづくりの醍醐味と売上だけではない継続の意義・やりがいを感じました。

− 清水氏コメント:日本には、こういった良いモノが各地にまだまだあります。
第2弾には、最高品質の檜を間伐する際に発生する枝葉を使用した「加子母ひのき」シリーズを、そして第3弾となる新商品は京都府の「和束茶」の展開を予定しています。
WANOWAというブランドを通じて日本各地の良いモノを、そしてその裏にあるストーリーを世に拡めて、地域のモノづくりの現場へ貢献していきたいと思っています。
つくり手を選ばないビジネスモデル

貴社の商品を通して原料のつくり手に光を当てているんですね
− 清水氏コメント:職人さんに限らず、幅広く光を当てていきたいと思っています。
例えば「JOY’N (ジョイン) 」というプロジェクトでは、福祉作業所で働く方々とその保護者、職員と一緒にハンドソープとサシェ (香り袋) をつくっています。

− 清水氏コメント:もともと、製造作業の一部を福祉作業所という障がいのある方々が働く作業所へ依頼していましたが、コロナショックの影響もあって福祉施設の方々の仕事も減少してしまい、これを救済すべく社内から発足の声が上がりました。
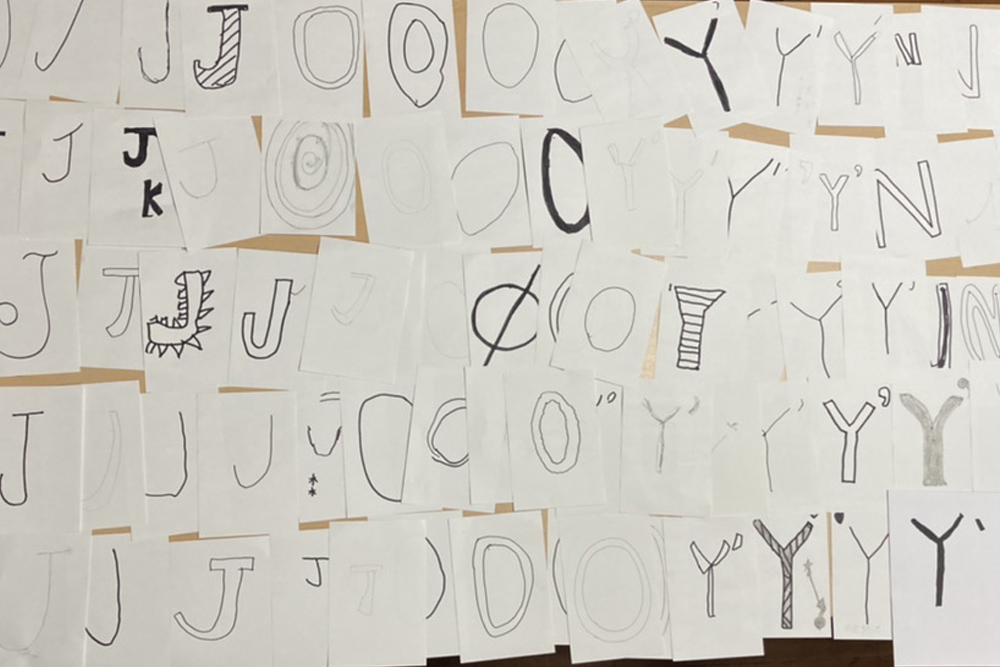
− 清水氏コメント:本プロジェクトも売上の2%を作業所へ還元し、継続的に行える支援プロジェクトとなっています。
また、多くの方にこうした現状を知ってもらえるよう、PRにも力を入れていて、ホームページからプロジェクトの様子をタイムリーで確認できるようにしています。
IT×香りで新たな顧客創造を

香りの会社として挑戦していることはありますか
− 清水氏コメント:AI技術を使ってオリジナルで香りがつくれるサービス「AISCENT (アイセント) 」を開始しました。
これまで「香りをつくるのが難しい」「自分の好きな香りがわからない」などの理由で、アロマなどの香りアイテムに手が出せないといった消費者に向けて、オンラインで手軽に楽しんでもらえるサービスをつくりました。
AISCENT (アイセント) 専用WEBサイトで香りがつくれるサービス。キーワードを選択し、季節やイメージを入力することでAIが自動で香りを導いてくれる。作成した香りレシピを元にディフューザーを注文したり、香りをシェアしたりできる。
− 清水氏コメント:先ほど紹介した「WANOWA」や「JOY’N」は、まずはキャライノベイトの香りアイテムを手に取っていただくところから始まりますよね。
より多くの人に手に取ってもらうため、“アロマに対してハードルを感じている方”にも試してもらいやすい、本サービスをリリースしました。
アロマの魅力を知ってもらうことはもちろん、毎日の料理のように、その日の気分や好みに合わせて香りを調合することができます。

− 清水氏コメント:香りアイテムがより幅広く消費者の身近なものになることで、ブランドやプロジェクトを横断して、今以上の成果が上げられると思っています。
我々が突破口となり商品に関わる方々に成果を還元していくためにも、本サービスがその一歩となれば嬉しいです。
他方、調香師のデータを元にAIを駆使することで、社内の生産効率が上がるというメリットもあります。
このようにA Iだけでなく、IT全般を上手に活用し、商品・サービスや流通、プロモーションなど販売店と一緒に発信していけるような企業になりたいです。

インタビューにお答えいただき、ありがとうございました。
モノづくりのあり方

「前職のとき、量産して売れないモノはゴミになる、という“モノを大事にしない姿勢”がすごく嫌でした」と語る清水氏。
これはライフスタイル業界に限らず、多くのメーカー・企業が直面している課題である。
日本の職人を追い詰めた“大量生産”というモノづくりのカタチが今、少しずつだが着実に見直されようとしている。
良いモノを長く使うということ、地元のモノを、ヒトを愛するということ、モノづくりがモノを粗末にする行為になってはならないこと――ここに立ち返ることで、続く文化や伝統を継承することができるのではないか。
つくり続けるための新しいカタチ

キャライノベイトの取り組みの面白さは、文化と伝統を守るためのモノづくりにおいて、積極的にITを取り入れる姿勢だ。
フレグランス企業でありながら、調香をAIに任せる大胆なサービスはその象徴ともいえる。
調香という最も重要に思われる役割をIT化させる理由――それは生産効率を上げることで、同社が最も重視している「ヒト・モノ・コト」の繋がりの開拓・活動に労働力を投資しているからである。
単純な売上効率ではなく、これから何十年先の日本の未来を見据えながらの取り組みは、近年ますます注目を集めている。

「最終的には、香りに縛られる必要はないと思っています。日本の伝統的なモノづくりのカタチを伝えていける手段であれば、どんどん新しいことにも挑戦したい」と語る清水氏。
新たな文化と伝統をつくるため、あくまでその手段のひとつとして「香り」が存在しているのだ。
何をつくるかではなく、何故つくるのか――新たなモノづくりの道が開けるのは、その問いの答えを見つけた時なのかもしれない。