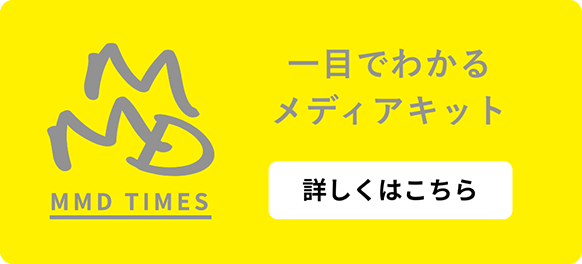Contents
ライフスタイルのすべてを豊かに彩るBAYCREW’S GROUP(ベイクルーズ グループ)

MMD TIMESは、セレクトショップとメーカーのためのワークメディアとして、今後の商品開発や販路開拓、売場づくりの端緒になるような取り組み・思考を伝えている。
今回は、BAYCREW’S GROUP(ベイクルーズ グループ)が手がけるインテリアセレクトショップ「journal standard Furniture(ジャーナル スタンダード ファニチャー) 渋谷店」へ伺い、商品開発と店舗運営について取材をおこなった。
JOURNAL STANDARD / journal standard Furnitureの店長とVMD経験を持つプレスの勝山龍一氏の話からは、アパレル企業が展開するインテリア業態ならではの取り組み・思考を知ることができた。

BAYCREW’S GROUP(ベイクルーズ グループ) 「創造を愉しみ、人生を楽しもう!」をスローガンに、人々に新しい価値を届けるべく“衣・食・住・美”の4つの事業を展開。「JOURNAL STANDARD」などのアパレル事業をメインコンテンツに、「J.S.BURGERS CAFE」などの飲食事業、家具・インテリア事業、フィットネス事業があり、ライフスタイルのすべてを豊かに彩る活動をしている。 「journal standard Furniture(ジャーナル スタンダード ファニチャー)」は、4つのカテゴリーの“住”の部分である、家具・インテリア事業である。
「journal standard Furniture」誕生から12年の歩み

アパレル企業がインテリアセレクトショップを始めたきっかけは何でしょうか?
− 勝山氏コメント: 12年前に「ACME Furniture (アクメ ファニチャー)」の前オーナーから譲り受けたのがきっかけです。
譲り受けた際に、“BAYCREW’S GROUPらしさ”を表現出来るインテリアショップを目指し、メインコンテンツであるアパレルブランドの「JOURNAL STANDARD」の頭文字を使った「J.S. Furniture」としてスタートしました。

− 勝山氏コメント: 現在は、ACME製品の専門店である「ACME Furniture」とインテリアセレクトショップである「journal standard Furniture」の2ブランドを展開しています。


オープン当初、苦労したことはありますか?
− 勝山氏コメント:オープン当初のJ.S.Furnitureのスタッフは、全員インテリア業界は未経験だったため、売場作りから接客まで全ての事が手探りでした。
特に接客は、洋服とは全く違う専門的な知識が必要ですし、洋服のようにその場でフィッティングができないので、お客様とより密な会話が大切です。売場も接客も試行錯誤を重ね、私たちらしい店舗を作ってきました。

どのようにしてJOURNAL STANDARDらしい売場や店舗を作っていったのですか?
− 勝山氏コメント: VMDを担当していた7・8年前は、まだファブリックアイテムを使って季節感を出すインテリアショップが少なかったので、アパレルブランドのJOURNAL STANDARDらしい“ミックススタイル”を取り入れた売場作りをしていました。
具体的には、洋服の生地を必ずどこかに入れるようにしたり、洋服を合わせる感覚でオリジナル商品とヴィンテージ商品と新着商品を混ぜて空間を作ったりしていました。


洋服に通ずる“ミックススタイル”の売場展開

インテリアのミックススタイルとは、どのようなものでしょうか?
− 勝山氏コメント: 単品で見るとジャンルの違うアイテムでも全体を見ると纏まりがあり、1つのスタイルとして成り立っているものを“ミックススタイル”と呼んでいます。
ファッションだとメゾンブランドに古着を合わせたり、バンドTシャツにスラックスを合わせたり、ジーパンに革靴を合わせたりするミックススタイルがあり、ジャンルを混ぜることで新たな魅力あるスタイルが作られます。
この考え方は、インテリアの売場においても同じことが言えるのではないでしょうか。

− 勝山氏コメント:インテリアの売場では北欧系のアイテムのみ展開したり、ミッドセンチュリー系のアイテムのみで統一したり、シリーズでまとめた見せ方が主流ですが、単品で見ると住み分けの違うテイストをミックスさせても、ラグや、クッションカバー、照明で全体感をまとめることで互いの良さを引き立てることができます。
journal standard Furnitureは、テイストやジャンルを統一せず、あえて混ぜて見せることで、私たちらしい独自の店舗を作っています。

− 勝山氏コメント: ミックススタイルの一例としては、「1つのダイニングテーブルに4脚とも同じチェアは展示しない」ことを実践しています。
来店されたお客様が自宅のダイニングテーブルと合わせることを想像して新たな発見や面白さを感じて頂けたり、購入されたお客様が「今日はどの椅子に座ろうかな?」と毎日楽しんで頂けたりする提案が、ミックススタイルの売場では可能になると考えています。
ファッションとオフィスから発想を得た、新たな市場

エンドユーザーの注目が高まっている商品を教えてください。
− 勝山氏コメント: 今期、お客様から注目が高まっているアイテムは、「ファブリックアイテム」と「機能性家具」の2つです。
まず、ファブリックアイテムは、本物のデニム生地を用いたカーテンが注目を集めています。
このリアルデニムのカーテンは、洋服の“デニムを育てる”のと同様に、使い込むほど色褪せなどの変化を楽しんで頂けます。生地にはペンキが飛んでいたり、ダメージ部分があったり、背景にアパレル業態があるからこそのデザインとなっています。

− 勝山氏コメント: 2つ目の機能性家具は、オフィス家具のような利便性を持ったインテリア商品です。
ヴィンテージ風のソファーに2口コンセントとUSBポートをつけた機能性ソファー「PSF COUCH SOFA」や、ソファーに座りながらパソコンを触れるように、天板が油圧で跳ね上がってくる無骨な雰囲気のセンターテーブル「PSF LIFTING TABLE」が人気です。


− 勝山氏コメント: 今の暮らしでは、ソファーで寛ぎながら携帯電話やタブレットを使ったり、リビングでパソコンを使ったりすることが多いと思いますが、そのような生活に合う家具は、まだ市場にあまりありません。
私たちのデザインするオシャレで機能的な家具は、これからも需要が増えると考えています。
顧客ニーズの把握で“長く愛用してくれるファン”を育てる

新たな取り組みや、今後の展望についてお聞かせください
− 勝山氏コメント: 最近の新たな取り組みでは、2019年11月22(金)にACME Furniture渋谷店がJOURNAL STANDARD FURNITURE 神南店としてリニューアルオープンしました。
「ACME Furniture」のアメリカンスタイルの家具・雑家の他に、より都会的で快適な生活を提案するjournal standard Furnitureの家具や、食器、植物、照明などを取り扱っています。
お客様のニーズを伺い、今までよりもゆったりとくつろげる店舗空間に生まれ変わりました。

JOURNAL STANDARD FURNITURE 神南店 住所 / 東京都渋谷区神南1-20-13 電話番号 / 03-5728-5355 (変更無し) 営業時間 / 11:00 ~ 20:00・不定休 (変更無し) J.S.Funiture instagram
− 勝山氏コメント: また、商品開発でも新たな取り組みをしています。小さめサイズのオリジナル家具を増やしています。
「都心部在住の洋服が好きなカップルやニューファミリー層で、40〜60平米の家」というのがjournal standard Furnitureのペルソナ設定としてあるのですが、お客様の話を伺うと、実際には想定よりももう少しミニマムな部屋で暮らしていることがわかったんです。

− 勝山氏コメント: このようなお客様は、journal standard Furnitureは好きだけどサイズが合わないという理由で家具の購入には至らず、雑貨のみの購入に止まっていました。
そこで “インテリアは好きだけど、なかなか手を出せない”ファンへ向けて、サイズが小さめで、価格帯も買いやすい家具を提案することにしたんです。
小さめの家具で豊かな暮らしを体感していただくことで、ライフステージが変わってもまたjournal standard Furnitureで買い替えたいと思ってもらえたら嬉しいですね。

インタビューにお答え頂き、ありがとうございました。
ボーダーレスな時代だからこそ、ボーダーレスなビジネスを

これから顧客になるであろう、ミレニアル世代の購買欲求をそそるものは“コト”である。しかもその対象は、非常に細分化されてきている。
ある特定のモノだけを持つのではなく、ファッションや食べ物、インテリア、デジタルツール、イベントなど様々なコンテンツをボーダーレスに組み合わせ、取捨選択し、自分らしい豊かな生活(=コト)を求めている。
デジタルネイティブであるミレニアル世代は、世界中とボーダーレスに繋がること、物事をボーダーレスに考えることが当たり前になっているのだ。

BAYCREW’S GROUPは、“常に新しい価値を時代に届ける”ことをミッションに掲げている。この姿勢が、勝山氏の話にあったように、アパレル・インテリア・オフィス家具という業界のボーダーを越えた商品開発や売場提案に繋がっているのだと感じた。
このようなボーダーレスなビジネス感覚は、メーカーにとってもセレクトショップにとっても必要ではないだろうか。
今の顧客だけではなく、今後を担う世代にもショップのファンになってもらうためにはどのような施策が必要なのか、勝山氏のインタビューをヒントに、ぜひそれぞれのショップやメーカーでも考えてみてほしい。